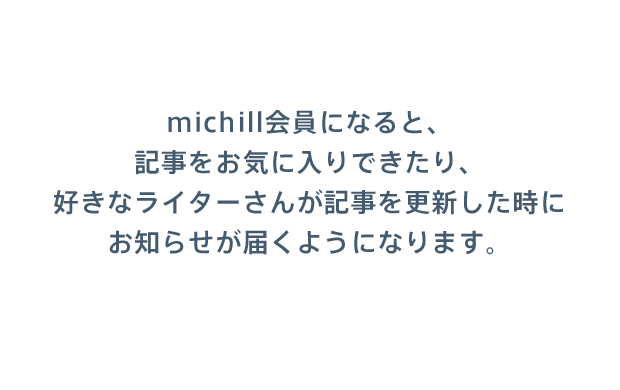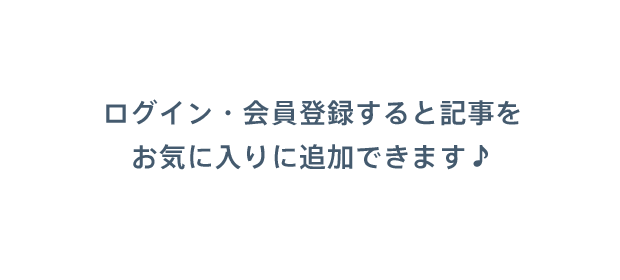北海道の山あい300人の地域に移住者が集まるワケ。生計や人間関係、住み心地などリアルを聞いた 岩見沢市
/

筆者の住む北海道岩見沢市の山あいの美流渡とその周辺地区には、小さなお店を開いたり、木工や陶芸などを制作し販売したりといった、自分なりの生き方を模索する移住者が集まっている。
美流渡地区は人口わずか330人と過疎化が進むが、なぜこのエリアに移住者が集まってくるのだろう?
共通する価値観は大量生産社会への疑問、そして自給自足的な暮らし方だ。この小さな集落で、いったいどのようにして生計を立てているのだろう。つねに安定した収入があるわけではないが、それでもなんとかやりくりをして暮らす、移住者たちの3つのケースを紹介する。
岩見沢市は北海道有数の豪雪地帯。朝、扉を開けると、膝上まで雪が積もっているということはたびたび。筆者は、道外からの移住希望者の地域案内をこれまで何度かしたことがあるが、雪の多さを知って「ここには住めない」と語る人は多かった。最寄りの駅まで車で25分。4年前に小中学校も閉校しており、商店も数えるほどしかないことから、「便利さ」や「暮らしやすさ」を求める人にとっては厳しい環境だ。

岩見沢が全国ニュースで取り上げられるのは、大抵大雪のとき。降り始めからの降雪量が2メートルを超え、自衛隊に出動が要請されたこともある(撮影/來嶋路子)
けれども、ここ4、5年の間にポツポツと移住者がやってきている。年に1、2世帯(ときにはそれ以上の年も)と数としてはわずかだが、美流渡地区の人口が330人、その周辺地域も含めて500人ほどと考えると地域への影響は少なくない。
そして移住者に共通するのは、大量生産・大量消費という価値観とは異なる生き方をしようとしているところ。ほとんどの場合、空き家をDIYで改修するなど、できる限り自分の手で暮らしをつくっていこうという意識をもっている。

酒屋や食堂など商店は数店。車で20分ほどの市街のスーパーまで買い出しに行く家庭が多い(写真撮影/來嶋路子)
今回、こうした人々の中から3組に、いまの暮らし方と、経済活動をどうやって営んでいるのかについて話を聞いてみることにした。
旅行先で空き家を見つけ、電撃移住した一家。ハーブティブレンドのお店「麻の実堂」笠原麻実さん「どうやって生きているのかと聞かれたら、自然に生かされているとしか言いようがない」。
そう語るのは、美流渡よりさらに山あいに入った万字地区で暮らす笠原麻実さんだ。笠原さんは、自宅の周りでオーガニックハーブを育て、ハーブティブレンドを販売する「麻の実堂」を営んでいる。
自宅の玄関先が小さなお店。このほかオンラインストアでも販売を行っている。

麻の実堂のハーブブレンド。もともとハーブティが苦手だったという笠原さん。そんな自分でも飲みやすいブレンドをつくりたいと日々研究を重ねている。滋味深い味わいが魅力(撮影/久保ヒデキ)
「自然に生かされている」という言葉は、ハーブという自然の恵みを活かしたものづくりを行うことはもちろん、暮らしのあらゆる部分に関係している。
暖房は薪ストーブ。夫の将広さんが、知り合いが所有している山で間伐を兼ねて丸太を切り出している。笠原さんは、時間を見つけてはそれを割って薪にする。
また春から秋にかけては山菜を採取し、食卓の一品に加えている。畑で野菜も育てていて、トマトピューレや味噌など保存食づくりにも精を出す。さらには、ヤギとニワトリを飼い、ミルクや卵も自給している。

5歳になる息子さんは、ニワトリやヤギと一緒に遊ぶ(撮影/佐々木育弥)

笠原さんはヤギのミルクと採れたての卵を使ったケーキをつくることも(撮影/來嶋路子)
笠原さんは、まるで何十年も前から農的暮らしを営んでいるように見えるが、実はそうではない。5年前までは、夫妻はともにショップの販売員として働きながら東京のマンションで暮らしていた。
移住のきっかけは突然訪れた。2018年、美流渡地区に移住した友人のもとを生まれたばかりの息子を連れて訪ねたときだった。
「2泊3日の旅でした。ここで過ごしているうちに私たちも田舎暮らしをしてみたいという気になって。そのときたまたま空き家を見せてもらったんです」(笠原さん)

紹介された空き家は2世帯がつながった炭鉱住宅だった。そのうちの1世帯に暮らしている(撮影/來嶋路子)
友人を介して見に行った空き家は、万字地区にある元炭鉱住宅だった。築50年以上経過していて、床が沈んで直さなければ住めない状態だったという。
しかし、二人の心は動いた。都会の暮らしには先が見えない閉塞感を感じていた。そして、帰りの飛行機に乗ったときにはすでに移住を決めていたのだという。
話はとんとん拍子に進み、家は無償で譲り受けることになり、東京の住まいを3カ月で引き払った。
「全部、東京に置いてきましたね。本当にあの家があるのだろうかと不安を抱えながらやってきました(笑)」(笠原さん)
旅行で訪ねた以降は下見もせず、地域がどのような場所かもまったく知らないという、まさに電撃移住だった。
移住後に、どうやって生活費を稼いでいく計画だったのかと尋ねると、「私はタイ古式マッサージができたので施術をしようと考えていました。それがうまくいかなくても、どこかでアルバイトしたっていいし、なんとかなると思っていました」(笠原さん)

夫が炭鉱住宅を改修。自宅でマッサージの施術も行っている(撮影/久保ヒデキ)
試行錯誤の中での暮らしが始まった。炭鉱住宅は住みながら改修したため、最初はキャンプのような毎日。内装は将広さんが手がけた。父親が大工だったこともあり、見よう見まねでやっていったという。
また、畑にも挑戦しようと、とりあえず直売所に苗を買いに行った。
「お店の方に恐る恐る『畑をやりたいんですけど、どの苗を買ったらいいでしょうか?』と聞いて、何も分からなくて土地の真ん中にポツンと苗を植えたんですよ(笑)」(笠原さん)

手探りだった畑づくり。毎年経験を重ね、多種多様なハーブと野菜を育てられるようになった(撮影/來嶋路子)
近隣には果樹園が多く、人手が必要だということが分かった。果樹は機械化が難しく、手作業に頼る部分が多い。二人は繁忙期に農園で働くこともあった。笠原さんは、自宅でタイ古式マッサージの施術も行い、冬季は将広さんが運送会社や除雪のアルバイトに出かけたりも。
「経済的な太い柱があるわけではなく、何本もの細い柱があって、ようやく暮らしている感じです」(笠原さん)

ハーブの焙煎は薪ストーブの炎でじっくりと。まろやかな味わいに仕上がるという(撮影/久保ヒデキ)
こうした中で、一昨年よりハーブブレンドティーの販売を開始。地域の閉校した校舎を利用したイベントに出展しクチコミで広がるようになった。昨年からはハーブを利用したワークショップも開くようになり、固定ファンもつくようになった。

お湯を入れたら、焦らずにじっくり蒸らす。この蒸らしが美味しいお茶をいれるポイント(撮影/久保ヒデキ)
ハーブに目覚めたのは、移住当初、出産後の体調不良で受診したクリニックの処置で、命の危険にさらされるような経験があり、薬や医療の在り方に疑問を感じるようになったことから。昔の人々の知恵や身の回りのものを活かして、体のメンテナンスができないだろうかと考えたという。
そして、ハーブや民間療法などの本を大量に読み、また畑で植物をじっと観察し続ける中で独自のやり方を編み出していった。

この日は朴葉(ほおば)をお茶にしてみた。松や桑、桜などさまざまな植物のブレンドに挑戦している(撮影/久保ヒデキ)
コンビニでものを買わなくなった。お金に依存しない暮らしに目覚めて現在、笠原一家の収入の約3分の1がハーブ関連とマッサージ。そのほかは、将広さんのアルバイトなどさまざまな仕事の積み重ねで成り立っているという。
東京時代よりも収入はかなり減っているそうだが、その分、余計な出費も少なくなった。
「家賃もかからないし、コンビニでお惣菜やお菓子を買ったりもしません」(笠原さん)
ただ、除雪機や車のメンテナンス代など、思いがけない出費がかさむときも。しかし、不思議にタイミングよくお金が回っているそうだ。こんな出来事の積み重ねからも、自分たちは「自然という大いなる力に生かされている」と感じずにはいられないのだという。
今後の目標は万字地区にごはんやを開くこと。万字地区の人口は80人で一軒も商店がない地域。だからこそ地元の人たちがいつでも立ち寄れる場所をつくりたいと、新たな空き家を取得して改修中だ。
「ハーブもごはんやも、しっかりとした形になるまでにはすごく時間のかかることだと思います。だから焦らずにやっていきたいですね」(笠原さん)

ワークショップ「魔女のお茶会」も開くようになった。参加者と一緒にガーデンで育てたハーブを収穫。それを使ってブレンドティーやボディクリームづくりをしている(撮影/佐々木育弥)
自分らしく、やりたいように進んでいけばいい。そう心から思えたのは、自然とともにある暮らしを始めたことが何より大きかったという。
「都会では、人と足並みをそろえなくてはならないと思ってとても窮屈な思いをしていました」(笠原さん)
家の裏につくったドラム缶風呂に入りながら、山あいの景色を眺めたり、タンポポやニセアカシアなど、山や野にある植物をサラダや天ぷらにしたり。その一つ一つが、生きているという実感をわきあがらせ、心を豊かに満たしていく。

ハーブはさまざまなところに生えている。「つんで匂いを確かめてみてください。すごくいい香りがしますよ!」と笠原さん(撮影/佐々木育弥)
各地を放浪後、木工作家として美流渡にアトリエを開いて。「アトリエ遊木童」木工作家・五十嵐茂さん「やっと出稼ぎに行かなくても、暮らすことができるようになった」。
上美流渡地区で「アトリエ遊木童」という名で家具を制作する木工作家・五十嵐茂さんは、笑顔で語った。
この地に移住したのは、およそ20年前。新潟出身で10代のころに単身で上京し、ライブハウスで働いた。20代でインドを放浪。38歳になって帯広の職業訓練校で家具づくりを学び、その後、美流渡に落ち着いた。アトリエを開く決め手の一つは土地代の安さ。当時、市が所有していた土地の借用料は年間2500円だったという。
五十嵐さんは自宅をセルフビルドし、妻の恵美子さんとここで暮らすようになった。

五十嵐茂さん。10・20代はミュージシャンを目指して活動したこともあった(撮影/佐々木育弥)
移住して5年ほどは、木工作品の制作とともに介護の仕事なども行っていた。
その後、東京の青梅市にある共同アトリエに所属するようになり、東京のクラフト市や百貨店などでの販売も行ってきた。
「北海道だけでは作品の需要が少なくて、『出稼ぎ』に出ていたんだよね」(五十嵐さん)

座面にさまざまな樹種を組み合わせて、カラフルな色合いを出したスツール(撮影/佐々木育弥)
こうした暮らしに変化がやってきたのは昨年。
笠原さんも出展した地域の旧校舎を利用したイベント「みる・とーぶ展」に参加したことだ。
このイベントは、地域でものづくりをする人々や、各地のミュージシャン、飲食店を営む人々など20組以上が集まって約2週間にわたって実施されている。
昨年は、春、夏、秋の3回開催され、合計で4300人が来場した。

「みる・とーぶ展」に出展。市内の「木工房ピヨモコ」との2人展を教室で開催した(写真撮影/來嶋路子)
このイベントで五十嵐さんは春に「おんがくしつ no 椅子展」を開催。
定番となっていたスツールをメインにした展示を行った。教室には時間が足りずに塗装まで仕上げられていなかったテーブルも置いた。購入希望者が現れたら、後日塗装をして届ける予定だった。
しかし、ここで思いがけない展開があった。
「テーブルの塗装を自分でやりたい。孫にじいちゃんがつくったテーブルだよと言ってプレゼントしたいんだ」という男性が現れた。
また、別の来場者からも、テーブルを一緒につくりたいので教えてほしいと頼まれたという。

無垢の板を使ったテーブル(撮影/佐々木育弥)
みんなでつくり、交流することの大切さを知って「これで分かったのが、完成品を売るんじゃなくて、みんなでつくるってことが大事なんだということ。時代は変わったんだね」(五十嵐さん)
夏のイベントでは「おんがくしつ no 椅子展」ともに、「組み木スツールワークショップ」も会場で常時行うこととした。
あらかじめ脚や座面のパーツはつくっておき、参加者は組み立てと仕上げを行い、4時間程度で完成するようにした。10名だった定員はすぐにいっぱいになった。

スツールづくりワークショップのチラシ。参加料は約2万円。通常の商品を買うよりもかなりリーズナブルな値段を設定した(画像提供/みる・とーぶプロジェクト)
商品をたんに販売していたころよりも、売り上げは伸びた。年3回の「みる・とーぶ展」の収益と、その場で受けた注文によって、今年は暮らしを回すことができたそうだ。
組み木スツールワークショップの評判は上々。自分でつくったという物語によって、その人にとって何倍も思い出深い椅子となっていた。
「椅子をつくっている間に、みなさんの人生について聞かせてもらいました。深く話ができたことが本当によかった」(五十嵐さん)

この地域に移住した画家・MAYA MAXXさんとのコラボも行った。五十嵐さんが額をつくり、それに合う絵をMAYAさんが描いた(撮影/佐々木育弥)
人々の物語を共有すること。それは五十嵐さんの喜びにもなった。そして過疎地でも人が訪れ、そこで作品を売って暮らせる可能性が開けたことは、大きな希望につながった。
「ここは元炭鉱町で、廃れていく一方だと思っていたけれど、近年になってパワフルな移住者がやってきて、まちの風景が変わっていくのを感じるよ」(五十嵐さん)
今後の目標は、彫刻も制作すること。木の中から現れ出た精霊のような不可思議な作品をつくっていきたいのだという。
自分でものをつくって販売し、生計を立てようとする移住者がいる一方で、札幌と美流渡の二拠点暮らしを選択する人もいる。
「平日に会社員として働いて、週末にはやりたいことを自由に試してみたい」。
美流渡で月に2回、週末に玄関先で古本屋を開く「つきに文庫」を営み、アフリカンダンサーとしても活動をする寺林里紗さんは、そんな風に考えている。

「つきに文庫」を開く寺林里紗さん。冬季は休業、春から営業を再開する(撮影/佐々木育弥)
札幌から車で1時間半ほどの美流渡を知るきっかけとなったのは、万字地区に移住したアフリカ太鼓の奏者の友人が、この地で定期的に太鼓教室を開催していたこと。参加者の中から「アフリカンダンスもやってみたい」という希望があって、その講師として寺林さんに声がかかった。

アフリカンダンサーとしてライブのステージに立つことも。美流渡地区でダンスワークショップも開催している(撮影/來嶋路子)
「美流渡は、山並みがまるで四国のようでいい場所だなあと思いました。それに、移住者のみなさんが、週末になるといろいろなイベントをやっていて、おもしろい人たちのいるところだと感じていました」(寺林さん)
以来、週末住めるような家を探すようになり、1年ほどして知人の紹介で空き家を見つけた。一部修繕も必要だったが地域の友人らの手を借りて整えていった。

2階の屋根裏から山々が見渡せる。その風景が気に入ったという(撮影/佐々木育弥)
寺林さんの家には、近所の子どもが遊びに来るようになった。子どもたちが楽しめるようにと、玄関先で古本屋を開いてはどうかとあるとき思った。絵本を用意し、地球環境や旅、暮らしのエッセイなど、これまで自分が読むためにと集めてきた本を並べた。
初めてお店を開けたのは2021年7月。友人が訪ねてきて本を手に取り「これください」と言ったとき、本の値段を決めていなくて戸惑ったという。
「まさか売れるとは思っていなくて(笑)」(寺林さん)

玄関先がお店。自分が読んだことのある本を並べている(撮影/佐々木育弥)
その後は値段をつけて販売するようになったが、商いをやっているという意識はあまりないという。玄関先がオープンスペースとなり、本を通じてコミュニケーションが生まれ、みんながのんびりと過ごせる場づくりを大切にしている。
「いま建築事務所で働いています。働くことは好きなんですが、ドジらないように、毎日すごく緊張していますね」(寺林さん)
寺林さんは社会人として働きつつ、週末の月に2回古本屋さんを開き、バンドやダンス活動も続けている。美流渡に拠点を設ける以前に、これまで2度、アフリカに2~3カ月滞在してダンスを学んだことがある。1回目は会社に長期の休みを取って行き、2回目は退職して向かったが、帰国後すぐに新しい就職先を探すことができたという。

古本屋を始めると、友人からさまざまな本が集まるようになったという。寺林さんは、それを一つ一つ読んでから、ラインナップに加えていく(撮影/佐々木育弥)
「ここに住む移住者のみんなは、以前とは暮らしを大胆に変えていますが、私にはそんな勇気はないので二拠点暮らしをしています。でも、いずれは美流渡に移住したいという想いももっています」(寺林さん)
場所を変えることによって仕事とプライベートの切り替えができるそうで、週末、美流渡へと車を走らせていくと、気持ちがゆるみ、ワクワクした感覚があふれてくるのだという。
子どものころから自然の中で過ごすのが大好きで、木登りが得意中の得意だったという寺林さんにとって、山あいのこの場所は生きるエネルギーをチャージする重要な場所になっている。
「空が広くて、四季を通じた変化があった。ここに来ると本当に心が安らぐんですよ」(寺林さん)

美流渡で木に登って、ヤマブドウの実を採ることも(撮影/佐々木育弥)
お金をどう稼ぐかではなく、地域や自然と関わる中からできることを探して今回紹介した3人のように、移住者たちは、地域の人々や自然と関わる中で、何ができるのかを探り、自分なりの活動を続けている。
笠原さんは、体調を崩したことがきっかけでハーブに目覚めた。寺林さんは、美流渡に本を置いてあるスペースがなく、子どもたちに喜んでもらえたらと古本屋を始めた。そして五十嵐さんは、この地で人々と触れ合う中で、完成品を売るのではなく、みんなでつくるという方法にシフトさせていった。

旧美流渡中学校で開催された「みる・とーぶ展」には「麻の実堂」、「アトリエ遊木童」、「つきに文庫」も参加。来場者の声から新たな工夫が生まれることもある(写真撮影/佐々木育弥)
みんなそれぞれ、作品や本が売れるようにと日々試行錯誤を繰り返しているが、収入がそれほど見込めないからといって、現在の活動をやめるわけではない。
共通しているのは、「お金が儲かるから」とか「得をしそうだから」という尺度で物事を選択せず、自分が「心からやりたいことかどうか」で動いているところ。
「貯金をしておかないと、先行き不安では?」と思う人もいるかもしれない。当然、多少の不安はあるだろうが、お金がなければ畑で食べ物をつくったり、農家の手伝いに行けば「きっとなんとかなる」と考えている人は多い。
また、家も自分たちで修繕すればいいし、電気やガスに頼りすぎずに薪を燃料にすればいい。ここで暮らしていくうちに、生きていくための力が自然に備わってきているのではないかと思う。

今回紹介した移住者たちは、日々、協力しあって生きている。イベントを共同で開催したり、アフリカ太鼓のバンド活動もみんなで行っている(写真撮影/來嶋路子)
「もう、都会のマンション暮らしには戻れない」と笠原さんは夫妻で語り合うことがあるという。地面の近くで暮らすことが、何より重要だと分かったそうだ。
都会で将来への安心を求めると貯蓄や投資、保険などという紙に頼る他はない。もちろん都会にいれば、公共施設や病院などが近くにあって利用しやすいという安心感もあるだろう。一方でこの地の移住者は、この大地とつながっていて、いつでもそこから恵みを受けることができるという安心感があるのだと思う。
●取材協力
麻の実堂
つきに文庫
【住まいに関する関連記事】
この記事のライター
SUUMO
177
『SUUMOジャーナル』は、魅力的な街、進化する住宅、多様化する暮らし方、生活の創意工夫、ほしい暮らしを手に入れた人々の話、それらを実現するためのノウハウ・お金の最新事情など。住まいと暮らしの“いま”と“これから= 未来にある普通のもの”の情報をぎっしり詰め込んで、皆さんにひとつでも多くの、選択肢をお伝えしたいと思っています。
ライフスタイルの人気ランキング
新着
公式アカウント