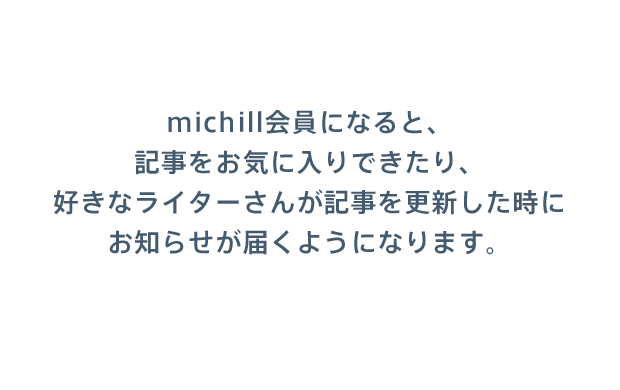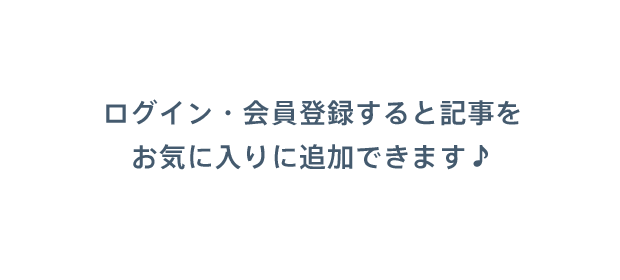人口3200人の小さな町で惣菜店なぜ始めた? ”地域内循環”の挑戦から1年 北海道下川町
/

都会に暮らしていると想像しにくいけれど、地方では1軒の店の存在が大きい。人口減や高齢化によって個人商店が閉店したり、チェーン店も撤退したり……といった状況が起き始めている。1軒でも「近くの街で買い物する」選択肢を増やし、地域内でお金がまわることが人びとの暮らしを左右する。まさにそれを体現するような事例が、北海道下川町で矢内啓太さんが始めたお惣菜屋「ケータのケータリング」である。小さな町で新しい店をオープンしようと決めた経緯と、矢内さんの背中を押した「地域内循環」の考え方にもふれてみたい。

「ケータのケータリング」の販売風景(写真提供/矢内啓太さん)
「地域資本のお店があった方がいいのかな」と北海道下川町へは、札幌から車で約3時間、旭川からは2時間かかる。お世辞にも便利とはいい難い場所だがそんな町ならではの、暮らしを維持していこうとする人びとの強い意思や工夫がある。自治体の画期的な施策もあって、いま移住者に人気のある町でもある。
人口3200人のこの町に2020年6月にオープンしたのが「ケータのケータリング」。矢内啓太さんが始めた弁当・惣菜のお店だ。矢内さんはおじいさんが創業した菓子・パン屋「矢内菓子舗」で家族や親戚とともに働いていた。
ところが2年前、町が開催した勉強会に参加して「域内経済循環」の考え方を知る。
「正直に言えば、こんな田舎の町内でお金をまわすなんて無理だと思っていました。外資本で全然いいんじゃないかって。でも地域内経済やレジリエンスの話を聞いて、それじゃいけないかもしれないと思うようになったんです。100%は無理でも、地元資本のお店を少しでも使うことで、自分たちの暮らしが豊かになったり、維持できるとしたら。地域でお金をまわすって案外大事なんじゃないかなって」

矢内啓太さん(写真提供/矢内さん)
「域内経済循環」とは、地域内でどれくらいお金がまわっているかを示す言葉だ。
たとえば観光や産業で町外からお金を稼いでも、コンビニなど外部資本の店や、ネットで買い物する割合が高ければ、せっかく稼いだお金が町内にまわらず外に出ていってしまう。ひいては、地元のお店が成り立たず、雇用も減り、ますます人口減や町の衰退につながり……といった悪循環に陥る。
さらにレジリエンスとは、災害など地域が困難な状況、危機的な課題に遭遇した際に、立ち直ることのできる力。とくに食やエネルギーの分野では自給率が高いほど地域のレジリエンスは高まる。
そんな考え方を知り、矢内さんは心を動かされた。
「ちょうどそのころ、町のスーパーが1店舗閉店することになって。みんなその店で買い物していたのに、お弁当や惣菜など買えなくなっちゃうねと話していて。コンビニはあるから弁当が買えなくなるわけじゃないけど、田舎なので会合とか総会とか、いろんなお弁当需要があって。全部その1店舗でまわっていたのが外部資本や町外に流れると。小さな町だけどそれって結構な額なんですよ。地域でお金をまわそうと考えると地域資本のお店があった方がいいのかなと」
これが矢内さんの背中を押した。
エネルギー自給率100%をめざす、下川町というユニークなまちもともと下川町は、地域内循環の考え方をもとに経済施策を進めてきた自治体でもある。1960年代の最盛期には1万5000人いた人口が、主産業の鉱山が閉山になるなど、30年間で激減。町は経済を立て直すために、より効果的な施策を打とうと、地域から漏れ出ているお金の実態を知るための調査を行った。

冬の下川町(写真撮影/甲斐かおり)
一般的に企業では、何にお金を使って、何で売上を上げているかを把握するのは当たり前のことだろう。だが自治体単位になると、地域内に数多くの事業者や住民が存在するので、どの分野でお金が外に出て、何でお金をどれくらい稼いでいるか、実態が見えにくい。
そこで下川町では研究機関の協力を得ながら、町内の主要な事業者に調査をして町の収支表をつくった。結果わかったのは、町のGDP(域内生産額)は約215億円あること。黒字部門は製材・木製品(約23億円)と農業(約18億円)で、赤字部門はエネルギー(約13億円)。その内訳は石油・石炭製品(約7.5億円)、電力(約5.2億円)といったものだった。
下川町は森に囲まれ、森林率が9割と林業の盛んな地域である。そこで、漏れ出ているエネルギーコストを町内でふさごうとエネルギー自給率を高める施策「下川町バイオマス産業都市構想」(2013~2022年度)が始まった。
その結果、2020年3月時点で町内には11基のバイオマスボイラーができ、公共施設の熱自給率が64.1%を達成。約1億円以上の流出を止め(2020年時点)、加えてカフェ、木工事業、トドマツ精油、エゾシカ加工、ボイラー熱を利用した菌床しいたけの栽培など小規模の産業・起業が起こり、年7000万円のビジネス創出、移住者の増加につながっている。
つまり、やみくもに事業を起こすのではなく、何に住民がお金を使っているかを把握した上で、そこをふさぐ新事業を起こしたという順番がポイントだ。

循環型の林業を行っていた下川町では木材が豊富(写真撮影/甲斐かおり)

バイオマス熱を活用した菌床しいたけの栽培も(写真撮影/甲斐かおり)
家計調査の結果が、惣菜屋を始めるきっかけに次に町によって行われたのが、一般家庭の家計調査だった。家庭内で、何をどこからどれくらい買っているか。それによって、町に残るお金、何の項目で外に漏れ出ているのかが大まかにわかる。漏れ出ている分野がわかれば、そこに新たな事業をあてがうことも考えられる。

2019年11~12月にかけて行われた下川町の「買い物調査」結果。回収調査票数308通(下川町役場提供)
結果を見ると、パンは比較的自給率が高い。町に人気のパン屋さんが3軒あるのが理由だ。ほか生鮮や弁当・惣菜類などの食品分野での漏れが大きい。
海のない下川町で「魚介類」が少ないのは仕方がないとしても「弁当・惣菜類」の分野で50%近くが町外のお店に漏れている。
この調査結果を知り、お惣菜屋を始めることを考えたのが、矢内啓太さんだった。
「数字だけではなくて、この時のアンケートで、惣菜屋がほしいといった声が少なくないと知りました。もちろんすべてを小さな地域内でまかなうのは無理。それを否定する気はないんです。
でもできることからやっていくのが重要かなと。僕がお惣菜だけでもチャレンジしてみるよって。そしたら、誰かが反応してほかの分野も立ち上がる可能性もある。全部じゃなくても、未来のためのお店が少しずつ増えていって、あれもこれも地域内でまわしてますって言えたら、下川の新しいインパクトになる可能性があると思ったんです」

「ケータのケータリング」のお弁当(写真提供/矢内さん)
「ケータのケータリング」はどんな店か?矢内さんは、もともと下川町の生まれ育ち。子どものころから、父親や叔父が働いていたパン屋で一緒に働きたいと思ってきた。札幌での修行期間を終えて、子育てが始まるタイミングでUターン。願い通り、父や叔父と一緒に「矢内菓子舗」で9年間働いた。
その後の惣菜屋としての独立だった。独学でオペレーションをつくり、妻と2人で店を運営している。地元の野菜を多く使ったお弁当は人気で、お惣菜も買える。お客さんは8~9割が地元のリピーター。週3回来てくれる人もいて、年配者も多い。日に平均すると20~30人。周囲の人たちに支えられて何とかやっている、と矢内さんは話す。
「コンビニで弁当買うくらいならうちのをと思うので、できるだけ温かいものを出したいと思ってやっています」
夏は野菜を仕入れる必要がないほど、近所の人たちからのおすそわけがある。家庭菜園にしては広い畑をもつ人が多いため、おすそわけも量が多い。先日は春菊を買い物かごに5つ分もらったという。
「この野菜をいただいたから献立をこれにしようとか。その都度工夫したり、下ごしらえして保存したり。おすそわけが多い夏と少ない冬とでは仕入れ額が数万円も差があるほど助かっています」

町内の農家からもらった春菊を使ったレモンサラダ。下川産のミニトマトも(写真提供/矢内さん)
タッパーを持参してもらうと50円引きになるサービスもある。お客さんの約1割はタッパー持参。よく知るお客さんだと、名前を書いてタッパーを貸したりもする。ご近所ならではの関係性だ。週の後半は、お母さんたちがお惣菜を買っていく頻度も高い。
「本来お弁当に求めるものって何より利便性だと思うんです。ぱっと買える手軽さとか。でも、うちがやっているのは真逆で。注文受けてつくるので待つ時間も少しかかるし、タッパーも洗う手間が発生する。不便を感じてる人もいると思うんだけど、あえてそうしているところもあって。でも小さな地域なので、弁当以外のニーズも多い。それにはできるだけ応えたいと思ってやっています」
地区の総会、ビールパーティーなど、まとまったオードブルの注文も入る。これからさらにテーブルスタイリングなども含めたサービス展開を考えている。

オードブルやお弁当の大量注文にも応じる(写真提供/しもかわ観光協会)
「森の寺子屋」が町内で新しいことを始めたい人を支援する場に矢内さんがケータリングの店を始める直接的なきっかけになったのは、役場に勤める和田健太郎さんが始めた「森の寺子屋」という勉強会だった。
「和田はもともと幼馴染で、町でいろんな新しいことが始まっていることを時々教えてくれていたんです。下川には移住者も増えて面白い人たちが集まっていて、それぞれやりたいことをいろんな形で始めていて。地元出身者として刺激を受けたところがあります」

「森の寺子屋」の様子。下川町内で「何かしたい」「新しいチャレンジを始めたい」と思っている方が有志で集い、月に1回学び合う試み(写真提供/和田さん)
森の寺子屋は、新しいことを始めたい人たちを支援する有志による勉強会。「森のようちえん」や、バイオマスの灰・下川の植物を使用した染めもの事業など、新しいサービスが次々に生まれる起点にもなっている。
お店を始める1年前、矢内さんはこの会に参加したことでパン屋をやめて惣菜屋を始める気持が強くなったのだという。
「最初はパン屋で新規事業を始められたらな、くらいの気持ちで参加したんです。でも家計調査の結果を見たり、レジリエンスの考え方を知ったりするうちに、地元の店が閉店することになって。すぐに買い物の手段がなくなるわけではなかったけど、地元のなかでまわるほうがいいんだろうなって、ごく自然に自分ごとにできたというか」
和田さんの話によれば、矢内さんは周囲からの「巻き込まれ力」があるのだそう。パン屋のころからイベント出店の機会も多く、地元の他の店とコラボレーションしたり、同級生と一緒に地産の食材をつかったイベント活動も行ってきた。

同級生と町内の食材、ハルユタカ小麦とフルーツトマトを使ってオリジナル揚げパン「グラーボ」をイベントで販売。2日で1000個売り切ったことも(写真提供/矢内さん)
「そういうことを地元の人たちに見てもらっていた上での惣菜屋なので、周りが応援してくれているんだと思います。地元だし、自分自身、下川が好きなので。家族で住み続けたいと思ったら、町が残り続けないといけない。できるだけ長く、子どもたちも、学校も残ってほしいし。できることはしたいなと思っています」
矢内さんが思っていた「小さな地域内で経済をまわすなんて無理だ」という考えは、ある意味で真実だろう。自分の生活をかえりみても、スマートフォンは手放せず、輸入された珈琲や大豆を日々消費して暮らしている。けれど地域内でお金がまわることは、同時にそこに仕事があり、多くの人の活躍の場があることを意味する。
ローカルで生き生きと暮らせる地域づくりをしていこうとする人が増えている今、欠かせない視点ではないかと思う。
●取材協力
ケータのケータリング
【住まいに関する関連記事】
この記事のライター
SUUMO
173
『SUUMOジャーナル』は、魅力的な街、進化する住宅、多様化する暮らし方、生活の創意工夫、ほしい暮らしを手に入れた人々の話、それらを実現するためのノウハウ・お金の最新事情など。住まいと暮らしの“いま”と“これから= 未来にある普通のもの”の情報をぎっしり詰め込んで、皆さんにひとつでも多くの、選択肢をお伝えしたいと思っています。
グルメ・おでかけの人気ランキング
新着
カテゴリ
公式アカウント