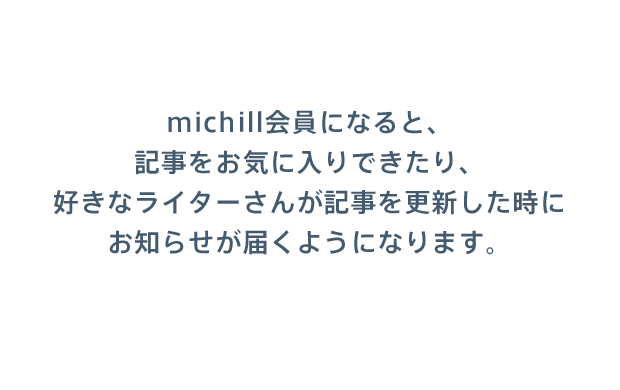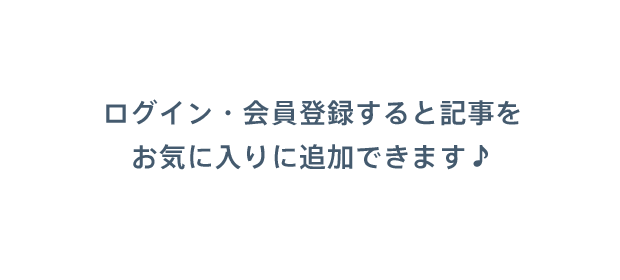施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[6] 築90年の邸宅を“自分の家”にして住み継ぐ
/
![施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[5] 築90年の邸宅を“自分の家”にして住み継ぐ](http://suumo.jp/journal/wp/wp-content/uploads/2017/05/132867_main-283x176.jpg)
相続の都合で解体されてしまう古く趣のある家を助けるには、そこに住むことが最良の手段である。とただ言うことは簡単ですが実際はそうもいきません。これからお話しするのは、築90年の邸宅を住み継ぐためにさまざまな難題に立ち向かう「住まい手」と「4組のプロフェッショナル」たち、この5者がひとつのチームとなり「逗子の家」を舞台とした約1年にわたる家づくりのプロセスです。【連載】施主も一緒に。新しい住まいのつくり方
普通、家づくりというのはハウスメーカーや工務店、リフォーム会社などのプロに施工をお任せするのが一般的です。ですが、自分で、自分の家づくりに参加してみたい人もいます。そんな人たちをサポートするのがHandiHouse。合言葉は「妄想から打ち上げまで」。デザインから工事までのすべてを自分たちの「手」で行う建築家集団です。坂田裕貴(cacco design studio)、中田裕一(中田製作所)、加藤渓一(studio PEACE sign)、荒木伸哉(サウノル製作所)、山崎大輔(DAY’S)の5人のメンバーとお施主さんがチームとなって、デザインや工事のすべての工程に参加するスタイルの家づくりを展開する。そんな「HandiHouse project」が手掛けた事例を通して、「自分の家を自分でつくること」によって、「住まい」という場所での暮らしがどういうものになるのかを紹介します。住まい手との出会い・住み継ぐための想い
JR逗子駅から徒歩10分。ゆったりと区分けされ閑静な住宅街のなかでもひときわ大きな邸宅が見えてきます。読売新聞社の社主や読売巨人軍のオーナーなどを務めた、読売グループの創始者、正力松太郎(しょうりきまつたろう)氏がかつて住んだ「逗子の家」。亡くなってからの約半世紀、空き家となっていました。
そんな家でもご多分に漏れず、相続の問題は訪れます。当初、親族の間で解体へと傾いていた方針でしたが、そこで手をあげたのが正力氏のひ孫にあたる40代のお施主さん。「自分が住むのであれば残すことができるのではないか」と連絡が来たのは2015年の春のことでした。
お施主さんとの出会いは4年前までさかのぼります。お施主さんは逗子の豊かな自然を舞台に「原っぱ大学」を主宰されていて、そのイベントでお声がけいただいたことがきっかけです。活動のコンセプトは「遊びを、自分でつくる親子に。」与えられるものではなくプロセスを共有し共につくり出していくという考えは、HandiHouseが目指す世界と同じものでした。
今回のプロジェクト、お施主さんには当初から明確なビジョンがありました。
1、既存の意匠を尊重し、可能な限り保存・修復し活用していく
2、見た目の改修だけでなく、骨格となる構造についても現代の強度まで引き上げ、安全性を確保する
3、新しい生活の中心となる場所は既存の意匠に合わせつつも、現代的な設備でつくり変えたい
4、自らもプロセスに積極的に参加し、自分の家になっていく現場を肌で感じたい
大きくわけるとこの4点です。
90年という時間をまとった凛とした美しいたたずまい、プロポーション、ディテール。素晴らしい既存の建物を最大限活かすこと、それだけではなく機能的に構造的にも現代の形に合わせ、新しい家族の新しい生活に合った場所を挿入することで、住み継ぐための舞台を整えたいという要望でした。

【画像1】改修前の和室から客間を見る(写真撮影/川辺明伸)

【画像2】改修前のキッチン(写真撮影/川辺明伸)
住み継ぐことを実現するために集まった4組のプロフェッショナルたちこの住み継ぐための想いを形にするには、改修範囲の広さや耐震強度を現代の基準まで引き上げることを求められていたことなどから、僕らHandiHouseだけの力では難しい……。ですので、今までとは取り組み方がかなり異なりました。「妄想から打ち上げまで」という合言葉の下、パソコンで図面を描くところから、現場が始まれば工具を持ち、実際の施工のほぼすべてを自分たちの手で行ってきましたが、今回のプロジェクトではそれぞれ専門分野の異なる4組のプロフェッショナルが集結しました。
●改修方針を導き出すプロ
住宅医として壊さずに既存住宅を読み解き、適切な判断を下す小柳理恵さん(和温スタジオ)
●構造設計のプロ
中高層木造も手がける木構造のスペシャリスト「桜設計集団」、佐藤孝浩さん
●施工のプロ
数寄屋建築などを手がける実力派大工集団の鯰(なまず)組
●施主参加型のプロ
プロセスに施主を巻き込み新しい居場所を共につくるHandiHouse project
通常、建物をつくる際は、建築士が設計したものを、元請けの施工会社が工事を受注し、下請けの業者・職人さんへ仕事を流す、お金を払うお施主さんを頂点としたピラミット型の体制で進むことが当たり前となっています。効率が良く、責任の所在も明確などメリットのある一方で、お施主さんは設計士や元請けの担当者など限られた人の顔しか見ることができません。しかし、このプロジェクトに元請けは存在しません。ここにお施主さんを加えた5組が横並びの関係でプロジェクトに向き合い、お互いをフォローし合いながら進行していくこととなります。
本格職人集団による施工から住まい手によるDIYまで具体的な改修計画、工事の流れとしては、(1)まず全体の既存住宅の状況を小柳さんが住宅医の立場から隅々まで調査し構造や劣化状況などを診断、(2)その結果に基づいて構造設計者の佐藤さんが現行の強度に沿うように耐震補強の方針を決め、(3)それを熟練の大工を抱える鯰組が施工を行いました。
耐震補強のため一度外したフローリングなども元通り張り直したり、外観にも影響を与える木製ガラス戸などは建て付けの調整のみとするなど、既存の素材・色・形に倣い、小柳さん監理の下に進んでいくこととなります。

【画像3】住宅医による既存状態の調査(写真撮影/小柳理恵)

【画像4】鯰組による耐震補強の施工(写真撮影/小柳理恵)
一方でHandiHouseが担当したのが、これから暮らす家族の居場所の中心として新しく挿入されるリビング、ダイニング、キッチンなどの場所づくりでした。既存のキッチンは女中室に隣接し、“裏方”としてつくられていたため、少し薄暗く決して居心地が良いとは言えませんでした。そこを機能的に現代に合わせて新しく更新し、内装の素材や色についても周囲の既存の雰囲気とかけ離れないように配慮しつつも、新しい家族の好みに合わせて設えました。
また、もうひとつの役割として、得意とする「共につくっていくスタイル」をこのプロジェクトにも持ち込み、小学生の子どもを含めた家族にできるだけ多くの時間を現場で過ごしてもらうようにすることでした。お施主さんの担当はフローリング張りと壁・天井のペンキ塗装でしたが、それ以外でもできるだけ現場に足を運んでくださいとお願いをしていました。
施工は鯰組もHandiHouseも同時に進行することとなります。最初は設計段階から顔見知りの僕らと一緒に手を動かすことが多かったお施主さんご一家。しかし、現場に通い詰め徐々に慣れていった結果、鯰組の棟梁をはじめとする職人さんたちともすっかり仲良くなり、3時の休憩のときにみんなでお菓子を食べたり、さらには急きょ、左官など一部の仕上げを手伝うことになってしまったり。
実を言うと、工事を行うに当たって不安がありました。それはHandiHouse流のやり方を、熟練の大工さんたちはどう思うかということです。プロの仕事に素人が手を出すなんで考えられないと見られてしまうのではと思ったのです。
しかし、実際はそうではありませんでした。ある日の夕方、学校終わりに現場に来た子どもたちを含めて家族総出で塗装工事をしていたとき、17時になり奥での作業を終えた大工さんがその風景を見て「いい仕事してるねー」と声を掛けてくれるということもありました。HandiHouse流のつくり方は、現代の価値観で成立しているのではなく、年の倍離れた大工さんでも共有できる普遍的な価値なんだと確信した瞬間でした。
こうして伝統的な木造建築を得意とする本格派職人集団の仕事と、お施主さんによるDIYという、両極端のものづくりが混然一体となって皆が完成を目指すというかつてないプロジェクトとなりました。

【画像5】お施主さん一家総出でペンキ塗り(写真撮影/HandiHouse project)

【画像6】家族の居場所の中心となるリビングのフローリング張り(写真撮影/HandiHouse project)

【画像7】お施主さんのDIYをのぞきに来た鯰組の大工さん(手前)(写真撮影/HandiHouse project)

【画像8】急きょ始まった鯰組、左官屋さんによる漆喰(しっくい)壁塗りレクチャー(写真撮影/HandiHouse project)
「プロの仕事とDIYの境界が見えてきました」お施主さんは当初から、「“ひいおじいさんの家”を自分の家とするためには」ということを考えていたように思います。向き合ったのは文化財にもふさわしいような本格数寄屋造りの邸宅。そこにとらわれず目指す方向に向かい適切に選択したチームと手法でよみがえらせ住み継ぐことの舞台を整えました。HandiHouseがチームにいることでプロセスに深くコミットし、自らも頭で考えイメージし、手を動かして仕上げていく。計画がスタートしてから住み始めるまでの約1年間で少しづつ自分の手の内に入れようとしているように感じました。
引き渡しを終えた後、お施主さんが、「子どもの遊びも、家づくりやDIYも同じですね」こんなことをポツリと一言おっしゃっていました。「子どもは親切丁寧に安全管理が行き届いた場所で遊ぶときは『危険』の判断力が鈍る気がします。一方で、自然のなかなど、自ら判断して動かなくてはいけない場所に連れて行くとかえって慎重に、自分の行動の限界ギリギリで遊ぶようになります。そのプロセスを経ていくと行動の限界を知り、境界を自ら押し広げていくことができるようになるんですね。家も自分でやってみるとプロとDIYの境界が以前よりもはっきり見えるようになりました。ここまでなら自分できるなとか、ここから先はプロに任せた方がよさそうだなとか」子どもの遊びも家づくりもプロセスを共有することの真ん中は同じだということです。
この気づきはお金を払った対価物・商品として家を見ていては得られない感覚です。DIYをすることで仕上がった空間に対する愛着が生まれ、つくり手と顔が見える関係を築くことでプロフェッショナルに対するリスペクトが生まれます。HandiHouseは良質な空間づくりをすることと同時に、お施主さんにこのような想いをもってもらうような人づくりもしていると思うのです。

【画像9】プロジェクトチームの集合写真。お施主さん一家(前)と、後列左から左官職人:大橋和彰さん、鯰組代表:岸本耕さん、和温スタジオ:小柳理恵さん、HandiHouse project:加藤渓一、鯰組現場監督:工藤順一さん、鯰組親方:向田八司さん(写真撮影/HandiHouse project)

【画像10】新しいリビング、ダイニング、キッチン。裏方として設えられていた既存のキッチン・ダイニングを仕切っていた壁を取り払い、新たに鉄製のガラス戸を設置し、明るく開放的で家族の居場所の中心として相応しい場所になるようにしました(写真撮影/川辺明伸)

【画像11】和室からダイニングを見る(写真撮影/川辺明伸)

【画像12】一度天井を解体し構造補強を施した2階の書斎(写真撮影/川辺明伸)
引越しを終え、新生活をスタートさせたある日、お施主さんから久しぶりに連絡がありました。
「丸ノコとインパクトを買いたいのだけど、どれを買ったら良いかな?」
ぼくらが理想とする家は「終わりが見えない家」です。それはかつて正力松太郎氏が住み、質の高い完成された家であっても同じことです。住まい手がこの家に主体的にかかわり続け、変化を楽しめる意識を芽生えさせるための良いスタートをつくること、それがHandiHouseの使命です。次の90年へ。住み継ぐということはまだまだ始まったばかり。
文/加藤渓一(studio PEACE sign)
●参考・原っぱ大学
・和温スタジオ
・桜設計集団
・鯰組
・HanduHouse Project●【連載】施主も“一緒に”つくる住まい 記事一覧
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[1] お任せはお断り!HandiHouse project流の家づくり
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[2] “即興ライブ”のような家づくり
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[3] 参加しないなんてもったいない。家族でつくる団らんの場”
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[4] 新築住宅を自分好みに“育てる”
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[5] 住む前から思い出いっぱいの家”
・施主も一緒に。新しい住まいのつくり方[6] 築90年の邸宅を“自分の家”にして住み継ぐ 住まいに関するコラムをもっと読む SUUMOジャーナル
【住まいに関する関連記事】
この記事のライター
SUUMO
177
『SUUMOジャーナル』は、魅力的な街、進化する住宅、多様化する暮らし方、生活の創意工夫、ほしい暮らしを手に入れた人々の話、それらを実現するためのノウハウ・お金の最新事情など。住まいと暮らしの“いま”と“これから= 未来にある普通のもの”の情報をぎっしり詰め込んで、皆さんにひとつでも多くの、選択肢をお伝えしたいと思っています。
ライフスタイルの人気ランキング
新着
公式アカウント